
■あらすじ
仕事バリバリの32歳OL、小島五和(こじま さわ)。28歳で最後の恋愛を終えてから、しばらく恋愛なんかしなくていいと思っていた彼女に訪れた30代最初の恋、そして失恋。その相手を見返すために、「恋愛マニュアル」を片手に、日々奮闘していく…
■作者プロフィール
志羽 竜一 1976年生まれ
慶應義塾大学 経済学部卒 東京三菱銀行退行後、三田文學新人賞を受賞してデビュー。
作品:「未来予想図」「アムステルダム・ランチボックス」「シャンペイン・キャデラック」など
※小説内で小島五和が使う「恋愛マニュアル」はNewsCafeトップページ中段リンクから閲覧可能です。
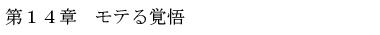
☆56
「お前、もしかして知らなかったのか」
電話口で傑が驚いた。私は携帯を片手に書店に向かって走る。ビッグカップルの不倫だけあって、その写真週刊誌はもう駅の売店やコンビニでは売り切れになっていた。
「いま香月さんから雑誌のこと聞いたの。傑も知ってたの?」
「あぁ……先週、店にも行ってきたよ」
「なんでよ、なんでそんな大事なこと私に教えてくれないのよ!」
「だって五和は知ってると思ったし。それにほら、最近は……」
傑は口ごもる。この前言い争いになってからなんとなく気まずくて、私たちは業務以外の話はしていなかった。
「お店はどうだったの」
「オレが行ったときは半分くらいは埋まってたけど。でも不思議なもんでさ、いつも賑わってるカノウしか知らないから、客席が半分空くともう雰囲気もまったく別の暗い店に見えてよ。本当に大変なのはこれからなんじゃないかな」
傑と電話したまま本屋に駆け込み週刊誌を探した。表紙に大きく俳優の名前が刷られている。その記事は雑誌の巻頭にあった。写真に写っている俳優を見て私は絶句する。やっぱり私の予感は当たってた。
「私のせいだ……」
写真に写っている俳優の洋服は、私が彼らをカノウで見たときと同じだった。
この写真は、私が昌弘さんとミュージカルに行った日の写真だった。デートをダブルブッキングして、加納さんとの約束をキャンセルするためにお店に行ったあの日だ。あのとき私はこの二人が入店していくのを見かけた。すぐにこの二人を追って入店した怪しげな中年の客が「予約はないが今から店に入れてくれ」とレセプションで揉めていた。きっとあの男がこの二人の写真を取ったのだ。
そしてその男に席を譲ったのは私だった。
「どうしよう、どうしよう!」
「落ちつけって」
「落ちついてられないよ!」
雑誌記事はこの二人の不倫を面白おかしく書き立てていた。有名人たちが出入りするカノウもその小道具に使われている。一般人の入店を拒否する自意識過剰なオーナーシェフ、この記者自身もはじめは入店を拒否されたと訴えている。客を選ぶ偉そうな店だけあって値段は目が飛び出るほど高いが、味はフランチャイズのカジュアルレストランに毛が生えた程度。もちろん美食好きの有名人たちにはその微妙な味の違いが分かるのだろうが……。
「加納さんはお客さんを選んでなんかない! 偉そうにしてもなければ、味だって誰にも文句を言わせない! ……それなのにどうしよう、全部私のせいだ」
「考えすぎだよ。たまたま運が悪かったんだ」
その書店に残っていた四冊をすべて買ってゴミ箱に投げ捨てた。
加納さんに謝らなくちゃ。この記事の写真が撮られたのは私のせいだ。その頃私は恋愛マニュアルを駆使し、昌弘さんを占領するために食事をし、その晩を一緒に過ごしていたのだ。
タクシーに乗り込んで行き先を告げる。運転手がバックミラー越しに私をなんどか見て「大丈夫ですか」と声をかけた。寒くもないのに体が震えてた。加納さんになんて謝ったらいいのかわからない、なにから謝っていいのかわからない。
タクシーを降りて螺旋階段を上る。ここまで来ておきながら、いま彼が仕事中であることにようやく気がついて、つくづく私は考えが足りないことを自覚する。恐る恐る螺旋階段を上り、店に入った。
「小島さん」
レセプションの男の子が私に気がついて会釈をした。彼の肩越しにフロアの様子が見える、そうして私は傑の言っていたことを理解した。
あれだけ沢山のお客さんと、彼らの幸せな時間で満ちていたお店はもう無くなってしまった。一番混んでいるはずの時間なのに、店内には空席ばかりが目につく。写真誌が出入りする店だと知って避けるようになった客がいるんだ。でも大きな変化はそこじゃない。客数よりももっと重大な変化。それは彼らの雰囲気だ。
彼らは素晴らしい料理を楽しめるお店に来たんじゃなくて、有名人の不倫に使われたお店に来ているのだ。会話のトーンが違う、店内を見まわす目が違う、料理を味わう表情が違う。そんなわずかな違いの集積がお店の雰囲気をまったく違う店のようにまで変えてしまった。ここにはもう私の知っている幸せに満ちた時間はなかった。私が大好きだったものが、加納さんが時間と情熱をかけて作り上げてきたものが、一瞬で消えてしまったんだ。
私はいろんな形で加納さんを傷つけてしまった。
そんなことなど、したくはなかったのに。
私はもうその場に立っていることができない。加納さんに謝る言葉も見つからない。
