
■あらすじ
仕事バリバリの32歳OL、小島五和(こじま さわ)。28歳で最後の恋愛を終えてから、しばらく恋愛なんかしなくていいと思っていた彼女に訪れた30代最初の恋、そして失恋。その相手を見返すために、「恋愛マニュアル」を片手に、日々奮闘していく…
■作者プロフィール
志羽 竜一 1976年生まれ
慶應義塾大学 経済学部卒 東京三菱銀行退行後、三田文學新人賞を受賞してデビュー。
作品:「未来予想図」「アムステルダム・ランチボックス」「シャンペイン・キャデラック」など
※小説内で小島五和が使う「恋愛マニュアル」はNewsCafeトップページ中段リンクから閲覧可能です。
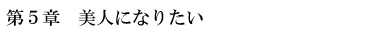
☆15
ジョギングスーツの袖に腕を通したのはほとんど一年ぶりだった。ランニングシューズ、ランニングキャップも去年のもの、イヤホンから流れるリズムも一年前のアジカンで、走りはじめると軽くタイムスリップした気分になった。一年前の自分へのタイムスリップ、あの頃はチーフに昇格して間もなかった。加那山に評価してもらえたのが嬉しくて、前にも増して仕事に集中するようになった。すでに学生時代の友人の多くは結婚していた。
二十代中盤の結婚の波が第一波とすると、三十直前に次の波がやって来る。第一波とちがって、第二波はビッグウェーブと呼ぶに相応しい大波だった。
「二十代での結婚☆」
という☆印のついた夢を抱く乙女たちを、あの大波は根こそぎ刈り取っていった。ちょっとほんとにその相手で大丈夫なの、と心配になるような相手でも、交際期間一年に満たず結婚する勇敢な乙女が大勢いた。豪快なライディングでその大波に乗っていった結婚ライダーたちの後姿を、私は呆然と眺めていた。ビッグウェーブの余波で揺れている水面にぷかぷか浮かびながら、同じように浮き輪で浮かんでいる乙女たちと一緒に肩をすくめた。すくなくとも、私たちが乗る波はあの波じゃない。そもそも波になんか乗る気もない。波なんかなくたって、自分のタイミングで自由に泳いで、飽きたら陸にあがるんだ。
そう思ってた。でも気がつけば恋愛もせず仕事に熱中して四年も過ごし、その前だって傑に言わせれば「恋愛の上澄みをすくい取るだけ」の不倫に二年も費やしていた。気がつけば会社では中堅で、後輩にオネエサマと呼ばれ、憧れの人には相手にもされない。私は自分が真冬の流木みたいに寂しく陸へ打ち上げられる姿を想像してぞっとする。
いかんいかん。これは過去へのタイムスリップじゃなくて、未来への踏切ジャンプなんだ。
そう思い直して私は顔を上げる。空高い秋晴れのお昼で、風も凪(な)いでいた。多摩川の川沿いをジョギングするにはこれ以上ない天気だった。それなのに走りはじめて数分も経たないうちに私の息はあがっている。一年間サボっていたツケをひしひしと感じた。三年前にはホノルルマラソンも走り切ったのに、いまやこの体たらくだ。手首足首に重量ベルトでも巻きつけているみたい。気持ちは前に進んでいるのに体がいっこうに動かない。
「とりあえず、今日はここまでにしよう」
と、音(ね)をあげたのはイヤホンのアジカンが三曲目を歌い終える前だった。十分も経っていないと思う。マラソンなんてもう二度と走れる気がしなかった。もう走ること自体やめようかな。ゴルフやテニスの方が華やかだし、世界も広がるかもしれないな。
「今日はもしかして、と思ったんですよね」
加納さんに挨拶をされたのは、私が多摩川に向かってジョギングとの決別をひとり宣言している最中だった。ノーメイクの上に疲れきった顔、全身汗まみれで多摩川に話しかけているところなんて誰にも見られたくなかった。でも加納さんはとくに気にした様子もなく笑顔で屈伸運動をはじめた。どうやらこれから走るらしい。
「約束守ってくれたんですね」
また走りましょうよ、と加納さんに言われたことを思いだして恥ずかしくなった。だって今まさに引退セレモニーをしていたところなのに。 レストランでは仕事着を着ていたからよく分からなかったけれど、ジョギングウェアを着た加納さんは相変わらず年齢を想像させないスポーツマン体型を維持していた。引きしまったふくらはぎは陽を受けて健康的に焼けている。シェフ帽をかぶっているときは見えないのだけれど、加納さんのトレードマークは短く刈り込んだ坊主頭で、それが小さい頭をよけいに小さく見せていた。
「いや、実は……もう走るのやめようと思っていたところで」
私が言うと加納さんは「そうなんですか」とうなずきながらストレッチをつづけた。なんだ、もうすこし残念そうにしてくれてもいいのに。と思う気持ちもあったけれど、まぁこの前会ったのも数ヶ月ぶりだし、ジョギングに関してはもう一年も一緒に走っていないんだ。なにも言えた義理ではなかった。
「お仕事は順調ですか? そろそろ忙しい時期ですよね。去年は今ごろからクリスマスのシャンパンイベントで準備されてたから」
「そっか、もうそんな時期ですよね、って自分が言うのも変だけど。そう、それも考えなくちゃいけないし、今度コンビニで仕掛ける商品があるんですけどその企画とかもあって」
加納さんに言われて仕事を思いだしているようじゃまずいな自分、とは思わない。それだけいまは他のことに集中している証拠だ。
「でも、ちょっといまは別のことで忙しくて。だから走るのもやめようかなーって」
「え! 走るのやめるんですか!」
といまごろになって加納さんはびっくりして、その驚きかたに私の方が驚かされる。「さっきも言ったんですけど」と私は笑った。
「そうだ加納さん、携帯の連絡先教えてください。私お店の連絡先しかしらないから」
言えた。想像以上に簡単に言えた。
「もちろん」
加納さんは携帯電話を取りだす。自分の番号を探しながら、でも、と彼は子供のような笑顔を見せた。
「でも、五和さんまた走ると思いますよ。一年間もブランクあるのに突然走りはじめるくらいだから」
「いーや、もう体が持たないんです。ゴルフかテニスに切り替えますよ。引退式にはカノウにお伺いするので飛びきりのご馳走作ってくださいね」
「喜んで。また走り出したくなるような料理を考えておきます」
彼は楽しげに言う。
彼の携帯電話の連絡先を登録しながら、自分が進化していることを実感する。以前はこんなにスムースにやりとりできなかった。いくら加納さんであっても自分から連絡先を訊くことなんてできなかったと思う。この感覚が体に染みこむまで、ジョギングのように一歩一歩確実に進んでいこう。はじめの壁ほど大きな壁はなく、その壁をもう私は飛び越えたのだ。
「連絡しますね」
ちゃんとそのひと言を残して、私は加納さんに手を振った。
ところで、なんで最後に「連絡する」と自分から言うんだ?
