
■あらすじ
仕事バリバリの32歳OL、小島五和(こじま さわ)。28歳で最後の恋愛を終えてから、しばらく恋愛なんかしなくていいと思っていた彼女に訪れた30代最初の恋、そして失恋。その相手を見返すために、「恋愛マニュアル」を片手に、日々奮闘していく…
■作者プロフィール
志羽 竜一 1976年生まれ
慶應義塾大学 経済学部卒 東京三菱銀行退行後、三田文學新人賞を受賞してデビュー。
作品:「未来予想図」「アムステルダム・ランチボックス」「シャンペイン・キャデラック」など
※小説内で小島五和が使う「恋愛マニュアル」はNewsCafeトップページ中段リンクから閲覧可能です。
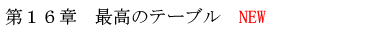
☆62
「トイレはあそこを右に曲がった左手です、気をつけてムシュウ」
おそらく加納さんはそんなようなことをフランス語で白人のお爺さんに言い、老人は笑顔で私たちの元を去った。
久しぶりに見た加納さん、トレードマークの坊主頭はそのまま、冬も本番になっているというのに日焼けのあとは前より濃くなったみたいだ。そのせいか少し痩せたようにも見えるけど、童顔を決定づけるくっきりとした二重と大きな瞳は、最後にあったときとなにも変わっていなかった。
「大丈夫ですか」
私をまじまじと見て加納さんが言う。加納さんをぼーっと見つめていた私は我に返って緊張した。ドレスが汗で濡れてるし、額を手で拭いたらなぜかマスカラの跡が指についた。自分の顔がいまいったいどうなっているのか恐ろしくて想像もしたくない。
「ちょっと待っててください、絆創膏もらってきます」
と加納さんが走っていって私はロビーに置き去りにされる。絆創膏? そんなものでいまの私の崩れたメイクは隠せないのに、と足元を見て納得する。ヒールのままずいぶん走ったから爪先と足首のストラップのところの皮が剥けて血が出ていた。転んだ覚えもないのに右肘もすりむいた跡がある。もしこれが私が十代の頃にやっていたトレンディードラマなら、ヒロインはどれだけ走っても美しいまま汗ひとつかかずに恋人の元まで辿り着けるのに。私は落胆しながらジミーチュウのヒールを脱いで片手に提げた。これ使ってください、と加納さんがフロントから持ってきてくれた絆創膏を貼った。
「五和さんどうしたんですか、今日イベントだったんじゃ」
「あの、それ抜けてきたから、このヒールはレンタルで、えっと、上手く走れなくて」
別になんで怪我したのかなんて加納さんは聞いてない。でもなにから話していいのか整理できない。私は自分の頭がどんどんまっ白になっていくのに、そのことを自覚しているのに、どうやって冷静さを取りもどすのかわからなかった。
「衣装と靴レンタルだったんだけど、血と汗がついちゃったら買い取りですよね」
えぇたぶん、と加納さんも困った顔をしてる。
「実はお店からお電話を頂いて、今日がコンクールの決勝だって知って」
「え、でもイベントは」
「傑に司会代わってもらいました」
「代わるって……」
加納さんはもういちど汗まみれの私を上から下まで見まわした。あぁ、どうしよう神様。なんて言う間抜けなんだろう。マニュアルだけに頼っていたら人を傷つけてしまい、反省し、後悔し、自分のまっすぐな気持ちで動いてみたらこのザマだ。己が不様すぎて嫌になる。お店に迷惑をかけたのを謝るタイミングでもなくて、愛を告白するにも非道い姿で、劇的に駆けつけるにはもうコンクールは終わってて、あぁ、あぁ、あぁ、と考えているうちに涙が両目にこみ上げて、完全に頭がまっ白になった私は、両手を広げると加納さんに抱きついてついに声をあげた。
「お疲れさまでした!」
自分でも意味がわからなかった。私は加納さんに抱きつきながら、自分が口にしてしまった間抜けなひと言に、涙が出た。加納さんごめんなさい、こんな大事なところで、しかも大勢の人前で。
「そのひとことのために、わざわざ……?」
「ごめんなさい、ほかになんて言ったらいいのかわからなくて」
あらためて自分の言葉が恥ずかしくなって私は加納さんの肩に顔を埋める。なんて大胆なことをしているんだろう。でももうきっとこれが最後だ、この体を離したら、すぐに背を向けてホテルを飛び出して、タクシーを拾って自宅に帰って熱いお風呂に入ってビールを飲んでから辞表を書こう。そう決めたときだった。
「ありがとうございます。来てくれてよかった」
加納さんが耳元で言った。
「五和さんに一番はじめに伝えたかったから」
「……なにを?」
加納さんが私の体を離して笑顔を見せる。
「実は、優勝を逃しちゃったんです。僕の料理は二位でした」
「そんな……」
私はここに来るまで加納さんの優勝を微塵も疑っていなかった。加納さんが優勝できないなんて考えることさえしなかった。加納さんが一番に決まってる、そんなの私のなかでは当然すぎるほど当然だったのだ。
「でも五和さんのために作った料理、ちゃんと認めてもらえたんです。審査員のフランスの評論家に気に入ってもらえて」
ほらさっきいた人、と言われて先ほど加納さんがトイレの場所を教えていた老人を思いだす。というかあれはトイレの場所を聞かれていた訳じゃないのか。
「どうやら、新しいお店を出すことになりそうです」
「それって……」
「日本じゃなくて、彼の本国です」
声も、でなかった。
私は嬉しさのあまり両手で顔をおおって、ぺたんとその場にかがみ込んだ。呼吸が苦しい、気がつくと涙が次から次へと溢れ出した。こんなに嬉しいことを表現する言葉を、私は知らなかった。もうこの場で大声を出して泣きたかった。
「さ、五和さん、どうしたんですか」
加納さんが焦って訊いた。嬉しくて、と答えるのが精一杯だった。加納さんは私の隣にかがみ込んで、ハンカチを手渡してくれる。加納さんの匂いがするハンカチだった。
「自分なりに最高のものを作ったつもりだったんで、正直優勝できなかったことは残念ではありますけどね。でも、たとえ審査員全員を満足させられなくても、たった一人に心から受け入れてもらえた方が嬉しくて」
「加納さん」
「五和さんのおかげです」
「あの、あの、私、加納さんに謝らなくちゃいけなくて、感謝しなくちゃいけなくて、ほんとうは加納さんに会う資格もないのも知ってて、加納さんが私の顔なんか見たくないのも知ってて……」
泣きながら話す私の言葉は途中で遮られた。今度は加納さんが、私を抱き寄せた。
「でも、会いに来てくれた」
私はついに大声で泣き出した。
「加納さんごめんなさい」
「来てくれて、ありがとう」
「ごめんなさい、しかもこんな姿で……」
私の背中の加納さんの手に力が入る。
「言ったでしょう? 五和さんが一番綺麗なのは、走ってるときなんですよ」
私は彼の肩に顔を埋めて大声で泣いた。彼は私が泣きやむまでずっと私の背中をなでつづけてくれた。呼吸が落ちつくと「大丈夫ですか?」と彼は柔らかい声で尋ねる。私は顔を上げる。ロビーの赤い絨毯が見えた。ホテルのお客さんたちはもう私たちのことを気にしていなかった。いい年した大人が泣き崩れ、座り込み、抱き合っているのをやれやれとでもいった顔で微笑みながら遠巻きで見ていた。
「加納さん、私、加納さんに伝えたいことが、たくさんあるんです」
彼はしばらく黙っていた。
やがてなにかを決心したように私の手を取ると、ゆっくりと立ちあがる。ジャケットを脱いで露わになっている私の肩にかける。その拍子にグゥと彼のお腹が鳴る音が聞こえた。加納さんは恥ずかしそうに坊主頭を手で掻いた。
「五和さん、ご飯は食べました?」
「いや、いや、まだです」
「ちょうど良かった。じゃあまず、ご飯を食べてからにしませんか?」
彼は走り終えた時に見せる気持ちよさそうな笑顔で言った。
「あなたと、一緒に食べてほしい料理があるんです」
私がうなずくと、加納さんは私の手を取ったまま出口へと歩き出す。夜空には雲にかかった銀色の月が出ていた。ホテルの前の車通りは多い。そうか、今年のクリスマスは金曜日なのだと私は気がつく。タクシーのドアが開く。私たちは最高のテーブルが待っている夜の恋路を走った。
