
■あらすじ
仕事バリバリの32歳OL、小島五和(こじま さわ)。28歳で最後の恋愛を終えてから、しばらく恋愛なんかしなくていいと思っていた彼女に訪れた30代最初の恋、そして失恋。その相手を見返すために、「恋愛マニュアル」を片手に、日々奮闘していく…
■作者プロフィール
志羽 竜一 1976年生まれ
慶應義塾大学 経済学部卒 東京三菱銀行退行後、三田文學新人賞を受賞してデビュー。
作品:「未来予想図」「アムステルダム・ランチボックス」「シャンペイン・キャデラック」など
※小説内で小島五和が使う「恋愛マニュアル」はNewsCafeトップページ中段リンクから閲覧可能です。
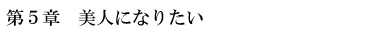
☆18
「どんどん頼んで。おごるから心配しないでいいから。ウニでもいくらでも、ほら私のトロもあげる」
「なんだよ、気持ち悪ぃな。休みの日に急に呼び出してメシおごるなんてよ」
「気持ち悪いってなによ」
私はムッとして言い返してから気を取り直し、大将に昆布じめを注文した。
「お嬢さん、気前がいいねぇ」
「やだお嬢さんなんて、ねぇ、傑、聞いた? お嬢さんだって。ほら食べて食べて」
「だからなんなんだよ、なんか頼み事があるんだろ」
自分の猪口(ちょこ)に注ごうとする傑の手から酒瓶をとりあげて、私が彼に注ぐ。
「あーもううっとうしいなぁ、早く言えって」
私は自分の猪口を一口で飲み干すと、パンと両手を合わせ目を閉じる。
「私、綺麗になりたいの」
「……気持ち悪ぃなぁ」
傑は顔をしかめていった。
「旦那、お嬢さんになんてこと言うんでぇ、気持ち悪ぃなんて言っちゃいけねぇ」
「ちがうよ大将、外見のことじゃなくてね、コイツがオレにご馳走してまで頼み事なんてしてくることが気持ち悪ぃんですよ」
「それにしたって他に言いようがあるだろう、不愉快だとか迷惑千万とかオトトイきやがれとかよ。お嬢さんに気持ち悪ぃだけは言っちゃならねぇと……」
「もう、うるさい! ウニ大盛り!」
へい、と大将は柏手を打って冷蔵ケースに手を伸ばす。
「大盛りってなんだよ」
「ちょっと聞いてたの? 綺麗になりたいのよ」
「それは分かったって。でもなんでオレにそんなの頼むんだよ」
私が顔の前で合わせていた両手を傑は払いのける。
「そんなこと言われたってなにしたらいいのか分からねーもん。会うたんび、綺麗になったなぁほんと、とか言ってればいいわけ」
「そうじゃなくて、あ、それもお願いしたいんだけど、でもそうじゃなくて」
傑に断られたら他に頼む相手を思いつかない。あした恋するキス講座は、いつも簡単そうで難しい注文をつけてくる。でも傑ならきっと私にピッタリの人を見つけてきてくれる。
「へいお待ち」
と出された軍艦巻きのウニは舎利(しゃり)からこぼれ落ちそうなほど山積みだった。
あした恋するキス講座いわく。
☆容姿を作り上げているのは、自分の『美意識』。
また、あした恋するキス講座いわく。
☆美意識は感化される。
中川紀美子たちからすれば、徹夜明けだとはいえほぼすっぴんのまま会社に顔を出すことが信じられないという。それは私と彼女の美意識の違い。
地元なら寝癖がついたままジャージ姿でコンビニに行ける人もいる、というかそれは私だけれど、でもアイメイクだけはしないと一歩も外へ出られないという人もいるし、部屋着では絶対に外に出たくないという乙女もいる。これも同じように美意識の問題だ。
容姿を磨くには、美意識を磨かなくてはいけない。
そして、新海英之は美意識は感化されるという。
つまり、美意識が高い人と一緒にいてその師匠から学ぼうとすれば、自分の美意識も見直されるというのだ。容姿を磨くには美意識を磨かねばならず、美意識を磨くには美意識の高い人に教えを請え、と。
「……と言っても、あまり難しく考える必要はありません。綺麗だと思う人、自分の見せ方を知っていると思う人に、アドバイスをもらうのです。それは自分の可能
性を広げていくことに他なりません」
その人に自分にあった洋服のスタイル、化粧のしかた、いい美容院、を具体的に指示してもらう。教える方も大変だし熱意が必要になってくるから、もし可能であるならプロを雇ってもいいという。プロのスタイリスト、プロのメイク、プロのヘアメイク、そしてそれらを統一させるプロのコーディネーター。 私にはプロの友達なんかいないし、プロを見つけたとしても幾ら払えばいいのか想像もつかない。どうしても友達ベースで頼める人を探すしかないけれど、美の師匠な<んてそう簡単に先生を見つけられそうにない。
とはいえ、ここで投げ出すわけにもいかない。
新海英之が言っていることも理にかなっていた。確かに今まで私は雑誌や本や店頭で洋服や化粧の知識を手に入れても、それらはすべて「自分好み」の知識でしかなかった。これは自分には似合わない、自分には興味がない、といって捨てられてきたものの方が遙かに多いし、誰かから具体的に「私のための」コーディネートなんてしてもらったことがなかった。意外と似合うのに、という可能性を私はすべて試すことなく破棄してきた。ほんとうならばそちらの方が容姿を引き立たせるかもしれないのに、自分で自分の可能性を制限してしまっていたのだ。
自分の美意識を高める。
自分の可能性を、見出してもらう。
これは自分でも楽しみだった。けれどその先生が思い浮かばない。私の周りにいる最もオシャレな女の子は中川紀美子だし、彼女に教えを請うなんて本末転倒だ。加那山も自分の見せ方を知っている女性で年齢にあったセンスの良いスタイリングをしているけれど、彼女に頼むなんて言語道断、仕事しないで何やってるの、と彼女の逆鱗に触れるに違いない。母親は南仏、しかも二十代の男と。
「でも傑ならそういう女の子知っているでしょ? ほらあなた女の子好きじゃない? 誰かいい先生を私に紹介して頂戴! このウニもあげる!」
