
■あらすじ
仕事バリバリの32歳OL、小島五和(こじま さわ)。28歳で最後の恋愛を終えてから、しばらく恋愛なんかしなくていいと思っていた彼女に訪れた30代最初の恋、そして失恋。その相手を見返すために、「恋愛マニュアル」を片手に、日々奮闘していく…
■作者プロフィール
志羽 竜一 1976年生まれ
慶應義塾大学 経済学部卒 東京三菱銀行退行後、三田文學新人賞を受賞してデビュー。
作品:「未来予想図」「アムステルダム・ランチボックス」「シャンペイン・キャデラック」など
※小説内で小島五和が使う「恋愛マニュアル」はNewsCafeトップページ中段リンクから閲覧可能です。
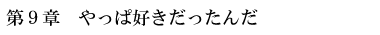
☆35
昌弘さん、トシ、キョロメガネくんたちのとのデートや、合コン。私のスケジュールは数ヶ月前とは比べものにならないほど華やかになった。それでもジョギングは週に三回以上は走るようにしているし、食事にも相変わらず気をつけている。炭水化物やスウィーツが狂おしくなるくらい食べたくなるときがあるけれど、ダイエットを始める前の自分の写真姿を思いだして崖っぷちで欲望を食い止める。もうあの場所へは戻りたくない。
傑も特に変わった様子はなかった。あれから香月も冷静さを取りもどしたのだろう。すべての歯車がきちんと噛み合っているような気持ちのよい日々がつづいた。週末にコースに出ると久しぶりに加納さんとも会った。準備運動をしていた彼にお邪魔していいですか、と私は挨拶をして彼の隣で一緒にストレッチをはじめた。
「今日は空が高くて気持ちいいから、いいペースで走れそうですよ。五和さんに置いて行かれないくらいには」
さぁどうかなぁ、と私は意地悪を言う。丁寧に体をほぐしている坊主頭の彼の姿から、あの隙のないシェフ姿はなかなか想像できない。もともと童顔の彼はジョギングをしているときは特に年齢が分かりづらくなる。
「こうしていると、大人になった野球少年みたいですね」
「子供っぽく見られないように無精髭はやしてるんですけど、ダメですかね」
「大丈夫ですよ、容姿と料理の味は関係ありませんから」
「それ、ひどい」
と彼が言って私たちは笑う。加納さんと話していると変に力が入らない。自分がいちばん気持ちいい状態で自分を表現できている気がする。
──それって好きなんじゃないの。
傑の言葉がとつぜん頭のなかに響いた。いまごろになって時限爆弾みたいに私の内側で炸裂した言葉に、私は顔がまっ赤になる。なんて言葉を仕掛けやがったんだ傑の奴。たしかに加納さんは素敵な男性だ。でもこれはジョギングであってデートじゃない。そんなの明らかだ。だいたい待ち合わせだってしていないし、食事も映画も電話もメールもしたことがない。たしかに連絡先は訊いたけれど、それ以外にはいままで加納さん相手に練習なんてしたことがない。というかそもそもデート相手には、スッピンで汗だらだらのこんな姿を見せてはいけないんだぞ! 女は隠れて綺麗にならなくちゃいけないって香月師匠も言ってたじゃないか!
──お前、自分でも加納さんのこと好きだって気づいてないんだ。
ともうひとつの言葉が、つづいて大爆発する。
「どうかしました?」
と加納さんに聞かれて、私はまっすぐ前を向いたまま「大丈夫です」と答えて走りはじめた。
ピリッと冷えた風が吹く。加納さんの言っていたとおり空が高くて気持ちのいい天気だった。私たちは準備運動を終えると、じゃあ行きますか、と声を掛け合って走り出した。
走っている途中から一緒になったり、どちらかの帰り際に出くわしたりすることはあったけれど、一緒にスタートするなんていつ以来だろう。はじめはどちらもペースを上げない。体を慣れさせるために歩くようなペースで足を動かしていく。体のなかに仕組まれたあらゆる小さな歯車たちに「目を覚まして」って声を掛けていくような時間。
「これくらいで走っているときって、はやく体が温まらないかなっていう気になりません?」
「あ、わかる。私は三十分くらいからが一番気持ちいいかも」
そして体の歯車がすべて噛み合う瞬間。
「自分はどこまでも走れるって、思いますよね」
そうそうそう、と私はうなずく。私はどこまでも走れる。風を感じ、空を感じて、蹴り上げる地面の確かさが、そのまま自分自身の確かさとなる。私は加納さんと視線があって、思わず笑顔がこぼれてしまった。
「そうそう、この前、五和さんに加納さんは挑戦するのが仕事だって言われたじゃないですか」
「あ、すいません偉そうなこと言っちゃって」
「そうじゃないんです。でね、実は料理のコンクールに出ることにしたんです」
と彼が説明したのは日本で開催される世界的なフランス料理コンクールのひとつだった。歴代の優勝者はそうそうたるメンバーで、優勝すれば本国フランスの料理界からも注目を受けることになる権威あるコンクールらしい。
「こういうのに参加するのって初めてなんですけど、出ようって決めたら毎日の生活にも張り合いがでて」
「うわ、すごい! 応援しますね、私」
「ありがとうございます。すごくワクワクしてるんですよ。なんかこう、間近に向かうべきものが現れて」
「わかる、それ! なんか時計の針をちゃんと自分の手で押し進めてる手応えっていうか、今日も生きたーっていう満足感っていうか」
「そうそれ!」
私たちは思わず大声を出してしまい、二人して恥ずかしくなって笑った。
「五和さんの場合はなんですか?」
「それは内緒です」
私はにっと歯を見せた。
「でも私なんかより加納さんの挑戦のほうがよっぽどすごい。頑張ってくださいね」
「えぇ、楽しみながらやってみます」
「それが大事」
私たちは前を向く。晴れた多摩川沿いをいつもより長い時間を掛けてゆっくりと走った。
