
■あらすじ
仕事バリバリの32歳OL、小島五和(こじま さわ)。28歳で最後の恋愛を終えてから、しばらく恋愛なんかしなくていいと思っていた彼女に訪れた30代最初の恋、そして失恋。その相手を見返すために、「恋愛マニュアル」を片手に、日々奮闘していく…
■作者プロフィール
志羽 竜一 1976年生まれ
慶應義塾大学 経済学部卒 東京三菱銀行退行後、三田文學新人賞を受賞してデビュー。
作品:「未来予想図」「アムステルダム・ランチボックス」「シャンペイン・キャデラック」など
※小説内で小島五和が使う「恋愛マニュアル」はNewsCafeトップページ中段リンクから閲覧可能です。
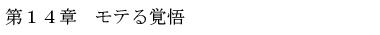
☆53
石鯛のカルパッチョも、フォアグラの低音炙りも、子羊のローストも、いつもにもまして素晴らしく感じた。お皿に描かれたソースデコレーションもどこか可愛らしい。きっと加納さんは、昌弘さんが私の恋人だと勘違いしてるんだ。もしくは、つき合うことに決めたのだと思ったのかもしれない。あたりまえだよな、あんな話の後に男の人と来ちゃってるんだもん。
「五和、もういいだろ」
昌弘さんが切り出したのは、加納さんからサービスされたメルローのボトルの栓が抜かれたときだ。ボーイは話を聞いていない素振りで淡々とワイングラスに赤くて重い液体を注いでいく。
「五和がわざと、じらすような態度を取ってるのは知ってたよ」
メルローを一口飲んで昌弘さんが言った。私が彼を気持ちよく振ってやろうと思っていたのに、思わぬ先制パンチを受けて私の全身に緊張が走る。私の行動がすべて計算されていたことを知ってた? 私は生唾を飲み込んだ。
「……それ、どういう意味ですか?」
昌弘さんはグラスの中のワインをゆっくりと揺らす。私はテーブルの下で指を組む。まさかマニュアルを読んで仕返しをしようとしていたことを昌弘さんは知っていたのだろうか。彼は私を焦らせるために充分に間を取ってから、優越感に満ちた目で言った。
「三ヶ月前、まだお互いに好きだって伝える前に五和と寝ちゃったことに怒ってるんだろ? それで俺に意地悪してじらしてるんだろ? もう意地悪は充分じゃないか。ここ数週間でおれの気持ちもわかったと思う。もう意地なんか張らずに、つき合おうよ」
私はテーブルの下の指を解いた。
たしかに昌弘さんは、私の態度が計算されていることを知っていたんだ。でも彼はそれを単なる意地悪だと思ってた。ほんとうは私が彼のことを好きで好きで最終的には交際したいと思っていると信じているのだ。
こいつ、バカなんじゃないか。
「な、もうこれでケンカはおしまい」
子供をあやすように彼は言う。私はそれが可笑しくて吹きだしてしまった。
「ケンカって、なんですか?」
「じゃあ、言いかた変えるよ。お互いに気持ちをじらすのはもうやめよう」
「じらすって。別になにもじらしてませんけど」
「そう言うなよ。お互い好きなんだ、もうこんな時間の使い方はやめようぜ」
「ちょっと、昌弘さん。すごく勘違いしてる。私、はじめから昌弘さんとつき合う気なんてありませんよ」
穏やかに笑っていた昌弘さんが固まった。
彼が信じていたものを、根っこから引き抜いた感じがした。
「ちょっと待てよ。そんなのおかしいだろ」
「おかしくないですよ。ぜんぶわざとやってたんですから」
「ぜんぶ……だと?」
「そ、ぜんぶ。はじめからお芝居だったんです」
昌弘さんの顔色が青くなったり白くなったり素早く変わる。この瞬間のために私は頑張ってきた。結局いまとなってはどうでも良くなってしまったけれど、それでも最後までやり通したのだと私は思った。
その後に、どんなことが待ち受けているか想像もしなかった。
昌弘さんは白くなった顔を、こんどはシーツに零れたワインのように鮮烈な赤に染めていく。唇が震えていた。彼の顔が奇妙に歪む。ゆっくりと立ちあがると、店に響きわたる大声で怒鳴り声を上げた。
「ふざけるな!」
あまりに急な大声に私は口を開けたまま全身を硬直させた。
「芝居だっただと? 俺をからかってたってことか!」
さらに大きな声を出す。店内中の人間が、ひとり残らず私たちを見てた。
「……怒鳴らないでください」
「なんのためだ? 仕返しか? 酔ってセックスした腹いせか!」
ボーイが昌弘さんを制止するが彼の耳には入らない。キッチンの扉が開く、その奥から異変に気づいた加納さんが顔を出すのが見えた。
「五和、なんとか言え!」
「……やめて」
「じゃあ週末のセックスはなんだ? あれもお前の手口だったってわけか、あ?」
「……」
「お前、人の気持ちをなんだと思ってるんだ! そうやって男を騙してなにが楽しい、もてあそんで傷つけるだけ傷つけて飽きたらポイか! いい気になるな!」
なにが起きたのか分からなかった。髪が濡れてる。赤い液体が滴っている。昌弘さんが目の前にあったワイングラスの中身を私の顔めがけてぶちまけたのだ。私はどうしていいのかわからない、なにを喋ればいいのか分からない、息が詰まり、両眼が熱くなる。
「この、売女が!」
自分の鞄を掴む。私は息を止めたまま、無言で私を眺める客たちの視線から逃げだした。
