
■あらすじ
仕事バリバリの32歳OL、小島五和(こじま さわ)。28歳で最後の恋愛を終えてから、しばらく恋愛なんかしなくていいと思っていた彼女に訪れた30代最初の恋、そして失恋。その相手を見返すために、「恋愛マニュアル」を片手に、日々奮闘していく…
■作者プロフィール
志羽 竜一 1976年生まれ
慶應義塾大学 経済学部卒 東京三菱銀行退行後、三田文學新人賞を受賞してデビュー。
作品:「未来予想図」「アムステルダム・ランチボックス」「シャンペイン・キャデラック」など
※小説内で小島五和が使う「恋愛マニュアル」はNewsCafeトップページ中段リンクから閲覧可能です。
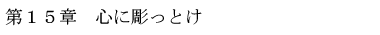
☆58
イベントには想像を遥かに超える入場の応募があった。今回一緒にイベントを組む各アパレルや雑誌、宝飾会社や音楽会社と協力して大きな宣伝戦略を展開したおかげだった。会場のスペースには限りがあるので入場者は厳しい抽選となり、メディアの注目度も高く、報道関係者席も割り当てを考えるのに頭を悩ませるほどだった。
母と話してから、私はすこし気持ちの整理がついた。
もちろん事態はなにひとつ変わっていない。社内で噂はまだ熱気を保っていたし、加納さんからもコールバックはない。でも、私の精神状態の急落は底を打った。こんな事態を招いてしまった原因がはっきりしたからだ。
私は恋がしたかった。
それなのに、私はモテようとしていたのだ。
そこには恋愛とモテることが直結しているという誤解があったし、昌弘さんと紀美子に仕返しをしたいという復讐心もあった。でもその誤解や復讐心が結果として自分から恋を遠ざけ、反対により多くの人を傷つけて迷惑をかけることになったのだ。
もういまとなっては噂なんてどうでもいい。ただ加納さんにはどうしても謝りたかった。しかし留守番電話にメッセージを入れて以来コールバックはない。もう加納さんも私とは話したくないのだろう。いま無理に彼に謝ったとしてもそれは私が楽になるだけの謝罪だった。自分でしてしまったことを、このまま自分で抱えていくしかない。
「おう、だれか探してんのか」
背後から傑(すぐる)が私の両肩に手をかけた。
ショーの開演までもう一時間を切っていた。場内は人で埋まりつつある。これから大舞台で司会をするというのに、不思議と私は緊張していなかった。あした恋するキス講座を閉じ、仕事に集中力を傾けて以来さんざん傑や制作チームと打合せをくり返してきた。やれるだけのことをやった実感はある。
「香月さん来てないかなと思って」
「遥に招待状送ったのかよ」
「そう。司会することになったの彼女のおかげだしね」
「戸田さん、ポスターの位置、あれで大丈夫ですか」
ディレクターが頭を下げて傑の元に駆け寄ってくる。スポンサーからも観衆からも見えやすい位置を傑は確認して修正案を出す。もう数ヶ月前までの傑はここにいなかった。営業部のエースとして業績を引っ張っていた頃以上の輝きを放って、彼はこのイベントに全力を傾けている。祐理さんとの離婚問題はあれから進展していないらしいけれど、愚痴はいちどだってこぼさなかった。精密なブルドーザーみたいにぐんぐんイベントを押し進め精度を高めていく傑は、瞬く間に社内での彼の評価を変えていった。いまではPR部の女子社員も彼の姿を追うようになった。
「ちょっと行ってくるわ。また後でな」
ディレクターと駆けていく傑の背中を見送った。
巨大な会場には全体を蛇行しながら横断する個性的な舞台が設置されている。ポージングポイントの四カ所は観客がどこにいても目にはいるように工夫されていた。あともうすこしで数千人の観客を前にしたシャンパンとファッションのコラボショーがはじまる。LEDの華やかな電飾の奥、壁一面を覆うディスプレイにはイベントのロゴマークが輝いていた。場内の客の多くはバーで提供されるプラスティック製のシャンパングラスを手にしていた。そのグラスの口から立ちのぼるシャンパンの甘い香りが会場全体の香水となる。
もし、この会場に加納さんがいてくれたなら。
きっとなんども飛び跳ねて喜んでくれただろう。
そう思って胸が痛んだ。あの人は私が着飾った姿よりも、スッピンで、汗まみれで走ってる姿のほうが素敵だと言ってくれてた。今日の私は着飾ってはいるけれど、このイベントは私が一心不乱に汗まみれになって作り上げたイベントだった。
「やっと見つけた」
と声をかけられて私の心臓は体から飛び出すくらい跳ね上がった。
「すごいなコレ。サワもスグルも頑張ったじゃん」
タイトな黒のデニムに、スワロフスキーでコウモリの意匠が施されたシャツを合わせた香月が立っていた。お洒落好きの女の子たちが集う会場内にいても、彼女は他に埋没しないオーラを放っている。あらためて自分の美意識の師匠に感心してしまう。
「苦しいくらいお客さん入ってるね」
「香月さん、VIPルームで見ます? もし必要ならパスを……」
「いい、私そういうの好きじゃないから」
香月は面倒くさそうに手を振った。
「フロアの雰囲気ってフロアにいないと絶対わからないしさ、上から見おろすのってなんか嫌なんだよね。やっぱ他のみんなと一緒に楽しみたいじゃん……あ、でも行きたい?」
と彼女は、隣にいた彼女と同年代の女の子に訊いた。白いニットのポンチョを羽織ったスタイルのいい女の子だった。香月と同じくらい顔が小さいのに、香月よりも身長が頭ひとつ高い。ラッシュという香月のお店の女の子なのだろう。一流のクラブには芸能人よりもよっぽど可愛い女の子が揃っていると言うけれど、その話は本当なのだ。
「私もここで平気。そんなに長くいないかもしれないし……」
声が細く、内気な印象だった。こんなことで接客が勤まるのかと私が変な心配をしてしまう。彼女を見やった香月が両手を腰に当ててため息をつく。
「またそんなこと言って。ちゃんと最後までつき合ってよ」
「でも……」
「スグルだって喜ぶと思うよ、義姉さんが来てるって知ったら」
「義姉さん?」
私は目を丸くして訊きかえしてしまった。傑の奥さん? 私の勝手なイメージの中では可愛いよりも綺麗系の気が強い女性だった。私の想像する傑の奥さん、というか、二十九歳の主婦のイメージと祐理さんはあまりにかけ離れていた。
「ごめんなさい、挨拶が遅れて。私、戸田さんといっしょに仕事をさせてもらってる小島五和です。いつもほんとうに戸田さんにはお世話になってて……」
「ほら、話したでしょ、私が仕込んだサワ。悪くないでしょ?」
「ちょっと香月さん! なんでそんなこと話してんですか!」
「だって義理の姉妹だもん。まだいまはね」
「遥ちゃん……」
と頼りなげに彼女はつぶやく。私は彼女がこの場へ来たことの意味を感じる。離婚調停に入ろうとしているのに、祐理さんはわざわざ傑の仕事を見るためにこの会場へやって来たのだ。
祐理さんは傑を傷つけた。でも彼女もじゅうぶんに苦しんでいる。打ちのめされた傑を見て、彼女は彼を再生させるには離婚しか方法がないと考えているけれど、きっと他にだって方法があるはずだ。実際にもう傑は仕事中にメロンソーダを飲んでいるだけの傑ではないのだから。
「あの、私いまから傑を……」
「小島さん、ここにいたんですか! 時間ですよ、加那山さんもさっきから小島さんのこと捜してて……」
アシスタントの女の子が私を呼びに来る。イベントの開始まで時間がない。私のドレスの裾を手で撫でながら香月は笑顔を見せた。
「いいから、サワ、行っておいで」
「でも……」
「グズグズすんな。今は仕事のことだけ考えろ」
香月が私の目を見ながら両耳をつまんで引っ張る。
私の頭のチャンネルが切り替わる。
彼女は私の肩をつかんで体をくるりと回すと、そのまま背中を押した。行きましょう、とアシスタントが駆けだしていく。私は香月にうなずくとアシスタントを追って走りはじめた。
「そうそう、ひとつだけ言っとくよ!」
背後から聞こえる香月の声に私は足を止めてふり返った。香月は私を指さして大声で叫ぶ。
「自信を持て! あんたは私の最高傑作なんだから!」
