
■あらすじ
仕事バリバリの32歳OL、小島五和(こじま さわ)。28歳で最後の恋愛を終えてから、しばらく恋愛なんかしなくていいと思っていた彼女に訪れた30代最初の恋、そして失恋。その相手を見返すために、「恋愛マニュアル」を片手に、日々奮闘していく…
■作者プロフィール
志羽 竜一 1976年生まれ
慶應義塾大学 経済学部卒 東京三菱銀行退行後、三田文學新人賞を受賞してデビュー。
作品:「未来予想図」「アムステルダム・ランチボックス」「シャンペイン・キャデラック」など
※小説内で小島五和が使う「恋愛マニュアル」はNewsCafeトップページ中段リンクから閲覧可能です。
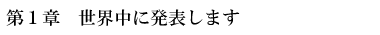
☆2
肩にかけた鞄を左手で押さえながら、駅へとつづく最後の一本道を私は全力で走った。時計を見る時間も惜しかった。祈るような思いで最終コーナーに建っているマンションをちらりと見あげる。
「……セーフ!」
マンションの五階、右端のベランダ、大きな観葉植物の隣にはパジャマ姿の男の子が歯を磨いていた。あの男の子はいつも朝の七時半ちょうどに歯を磨いている。彼がまだ歯を磨いているならば、私は電車に間に合うはずだ。私はぐっと力を入れて鞄を抱えなおし、駅までのラストスパートに入った。
毎週月曜日、私の部署では朝八時から早朝ミーティングがある。
いまどき銀行じゃないんだからそんな早くから仕事しなくても、と思うのだけれど、うちのPR部では加那山(かなやま)智子が決めたルールは国民憲法よりも重い。
「いい仕事をしたいのなら、誰も働いていない時間から働いて、みんなが働いている時間に遊びなさい」
それなりに筋は通っていると思う。でも加那山マネージャーの仕事の流儀はそれじゃ終わらない。
「そして遊びを切りあげたら、遊んだ時間の正確に二倍、もういちど仕事に戻ること」
彼女の流儀に沿えないなら、このPR部では生き残れない。
「じゃあ、いつ眠るんですか」
去年、新入社員の女の子が加那山に言い返したときに、部員はいっせいに凍りついた。最近の若い子が怪物に見えるのはこういうときだ。あんな可愛らしく人畜無害そうなのに、するっと恐ろしいことを口にする、怖いものなし。
「睡眠は食事と同じくらい大切よ」
「それだったら……」
「だから、食事に充てる時間と同じ時間だけ、睡眠にあてなさい」
「それって……。四時間も眠れません」
「そうね。きっと、あなたの服のサイズももうすこし下がるわ」
新入社員の女の子は顔をまっ赤にして震えてた。
「そんな働いていたら彼氏とだって会えないし。いまだって時間がなさすぎるって怒られているんです」
「技術の問題でしょう」
若干二十二歳の女の子は、なんのことを言われているのかすぐにわからなかった。
「ベッドの技術の問題よ」
加那山はちらりと横目で彼女を見やる。
「彼が怒るのは、わずかな時間でも彼が満足できるようなセックスを、あなたが与えられてないからでしょう?」
その新入社員は一週間で会社を辞めた。きっとあの瞬間、新入社員に限らず部員たちは全員自分のベッドでの技術がどれほどのものなのか、まっ青になって思いかえしたに違いない。
と、ここで言っておきたいのだけれど、私が何年ものあいだ加那山の下で働けているのは、ベッドの技術が長けているからじゃない(むしろそんな自信、ぜんぜんない)。加那山智子の下で私がある程度認めてもらえているのは、逆になんの才能もないからだった。業界中にその名をとどろかすキャリアーウーマンの天才みたいな加那山と仕事をするには、本当ならば彼女が持たない特殊な能力を持つ必要があった。たとえば、何カ国語も話せたり、専門職なみのパソコン知識を持っていたり。能力だけじゃない、とびぬけた容姿の美しさを持つ女の子はクライアントとの交渉の席に重宝されたし、体力のある男性社員は文字通り遊びも仕事も不眠不休であたれた。
でも。
容姿も体力も能力もすべてが凡庸な私にできたことは、プライベートの時間をそっくり削って、持ち時間のほとんどを仕事にあてることだった。私には、あの新入社員の言っていることがわかる。食事や睡眠の時間は必要、人間関係だって維持していくにはやっぱりそれなりの時間を割かなくちゃいけない。──だけど。恋愛なんかしなくても、人は死なない。私の場合、まっさきに切り捨てたのは恋愛だった。だからあの新入社員のようにベッドの技術なんかなくても平気だった。どんな恋愛問題よりも仕事を優先したし、最後の恋人と別れてからの四年間はほかの誰よりも仕事に集中できたと思う。自分の時間なんてほとんど無かったけれど、それでもいいと私は思った。加那山からPR部のチーフに選ばれたときには、私の二十代後半がようやく報われたと思った。
「五和、自分で会議の時間を決められるようになったなんて、立派になったのね」
だから、このお叱りの言葉は余計にひびいた。
ギリギリ間に合う時間に電車に乗れたはずなのに、結局私は会議に遅刻してしまった。
「すいません」
私は力なく頭を下げて謝った。
ほんとうは電車の時間には間に合ったんです、なんていう言い訳はもちろん通じるはずがない。エスカレーターの真ん中に立っていた若い女の子が携帯メールに夢中になっていたものだから、エスカレーターの行列が詰まっていたのだ。
「ちょっと、すいません」
と声を掛けてもイヤホンをしていて聞こえている気配もなかった。ホームに出たときには電車はすでに動き出してしまっていた。私だけじゃない、電車に乗れなかった他のサラリーマンたちも、エスカレーターをふさいでいた女の子を恨めしく眺めてた。彼女はそんな視線にも気づかずに携帯を覗き込みながらホームを歩いていく。これだから最近の若い女の子は怪物なのだ。
そして、その怪物は、間違いなく私たちの敵だった。
「五和さんが遅刻なんて珍しいですね」
声を潜めて紀美子が話しかけてくる。カーキのミニスカートに襟の大きめな白いシャツを合わせていた。黒く艶のあるショートヘアを、プロに仕上げてもらったかのように上手にスタイリングしている。白い肌、上向きの豊かな唇、すこし茶がかった大きな瞳、身長こそそれほど高くはないけれどモデルや芸能人のように華がある。
「昨日デートだったんですか?」
「そんなんじゃないわよ。会社に出てたの」
私は昌弘さんのことを思いだし、ちょっとうわずった声で答えた。まだ昌弘さんとのことは会社の中で誰も知らないし、彼といちど話すまでは気づかれてはいけなかった。
「昨日もお仕事してたんですか? すごい、見習わなきゃ」
と言って彼女はいつもの笑顔を見せる。
私はその笑顔に震えてしまう。
この中川紀美子こそ、怪物たちの親玉だった。白熱した交渉の最中でさえ男性クライアントに一瞬で議題を忘れさせてしまう、紀美子の完璧な笑顔。自分がいまどんな表情をしているのかを常に把握している二十六歳の女の子だった。毎年年末にあるクリスマスシャンパンの発売イベントの仕事で、去年紀美子は司会を務めた。五百人規模で行われるこのイベントの顔となった紀美子は、もはやうちの会社の看板と言っても過言ではなかった。
「でも、彼氏も寂しいでしょうね、五和さん忙しくて」
私に彼氏がいないのを知っているのに、平然と彼女はこんな会話をふってくる。普段だったら悔しくて仕方がないのに、今日は余裕を持って彼女に笑顔を返せる。
「五和、先週の報告。手短に」
と加那山から声が飛んで私たちは黙った。
私が小さくため息をつく横で、紀美子がくすりと笑うのが見えた。
