
■あらすじ
仕事バリバリの32歳OL、小島五和(こじま さわ)。28歳で最後の恋愛を終えてから、しばらく恋愛なんかしなくていいと思っていた彼女に訪れた30代最初の恋、そして失恋。その相手を見返すために、「恋愛マニュアル」を片手に、日々奮闘していく…
■作者プロフィール
志羽 竜一 1976年生まれ
慶應義塾大学 経済学部卒 東京三菱銀行退行後、三田文學新人賞を受賞してデビュー。
作品:「未来予想図」「アムステルダム・ランチボックス」「シャンペイン・キャデラック」など
※小説内で小島五和が使う「恋愛マニュアル」はNewsCafeトップページ中段リンクから閲覧可能です。
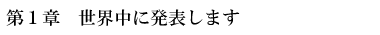
☆1
きっと、私は子供の手をひいていたと思う。
帽子をかぶった男の子は、反対側の手をお父さんとつないでる。私たち三人は、晴れた休日の並木道を歩いてる。子供は父親を見上げてなにかをおねだりする。父親は白い歯を見せて笑うと、私をふり返る。
「しょうがないな、もう一回。いい?」
私の旦那さんは、きっとそう言うと思う。
私は自分の子供に笑顔を向けて「いくよ?」と訊く。子供はうん、と嬉しそうにうなずく。
「いっせーの、せ」
私と旦那さんは、両側から、子供の手を引っ張り上げる。
子供の体が宙に浮かんで、家族の楽しげな声が並木道に響く。子供の瞳は父親に似ていて、子供の唇は私に似てて、子供が笑うと夫婦二人が同時に笑ったように見えたと思う。
私はきっと幸せだった。
それが私が若いころに想像していた、三十二歳の自分の姿だった。
と、私は心地よいうたた寝から目が醒めて、その瞬間に風呂水を一気に飲み込んだ。激しく咳き込んで必死に体勢を立て直す。狭い浴槽のなかで肘と膝を打ちつけて、もがくようにして上半身を外に出した。
「……死ぬかと思った」
幸せな夢を見ながら風呂場で溺死とかありえない。
まったくひどい夢を見たもんだ。あれはいつ頃想い描いていた自分の未来像だっただろう、たしか学生時代はよくそんな将来を想像していた気がする。女友達と未来の理想の家庭について何時間も話し合ったりして。……いや、私が想像していたラデュレのマカロンみたいに甘い幸せは恥ずかしくて友達にも言えなかったっけ。将来なんてどうなってるか想像もつかないなー、なんてうそぶきながら、実はものすごくディテールまで彫り込んだ将来像をひとりでむっつりと想像してたと思う。
あの頃、だれよりも自分が一番幸せになれる直感が、私にはあった。
確かにそう思ってた。
いま思うと、相当恥ずかしいけれど。
きっと、昨日までだったら風呂場でこんな夢をみた日にはかるく一週間は落ち込んでしまったと思う。三十二歳で、独身で、四年間彼氏がいなくて、そのぶん仕事に熱中してきた私。後悔なんてしていないし、胸を張って仕事をしている自分が好きだと言える。
──だけど、どこかで不安に思ってた。
幸せな奥さんである自分の夢なんか見てしまったら、今の自分が、かつての理想から遠くかけ離れていることに、風呂水を凍らせてしまうくらいの鳥肌を立てていたに違いない。
──でも。今日の私はそうじゃない。
なんてったって、私にはいま、彼氏(候補)がいる。
世界中に発表したい、というか、します、私にはいま彼氏(候補)がいる!
この四年間、結婚をしていない、彼氏がいない、というかそもそも好きな人がいない、という理由だけでどれだけ息苦しい思いをしてきたか。若い女の子から白い眼で見られて、男の子からは余計なくらい気を使われ、「だれかいればそれはそれで楽しいと思うけど、ひとりでも平気なんだ」と自分でもなんでもない素振りをする必要があった四年間。もし時間が戻るのなら、過去の自分を抱きしめてあげたい、そして背中をさすって、髪の毛を撫でて、私の耳元でささやいてあげたい!
「心配しないで、もう怖がらなくていいの、震えなくていいの、あなたには、あなたには、誰よりも素敵な彼氏(候補)ができるから!」
と私はシャワーを握りしめて、右腕を高く振り上げた。いつだって現実は想像を上回るんだ。私はシャワーの水をもごもごと口に当てながら思った。
小暮さん、いや、あえて今日からは昌弘さん、私より十歳年上の営業部のマネージャーで社内中の女の子が憧れる爽やかなイケメン。その昌弘さんが、まさか私の彼氏(候補)になるなんて想像もしていなかった。そりゃまだ(候補)だけれど、この(候補)だってすぐにとれるに決まってる。私たちはもう大人なのだ。そんな猶予期間なんて邪魔なだけなのだから。
たまたま昌弘さんも休日出勤をしていたのがきっかけだった。
昌弘さんと飲むなんてはじめてだったから、私は緊張して、緊張して、緊張のあまりボルドーワインを急ピッチで飲み進めてしまった。昌弘さんもかなり酔っていたと思う。ボルドーのボトルが空くと、新しく出された小さなグラスに貴腐ワインが注がれた。甘い香りが私たちの頬を撫でた。腰に手を回されていたのにもしばらく気がつかなかった。大量のアルコールはいままで二人がそれぞれの胸に隠していた宝石箱を探り当てた。その宝石箱の中には素敵な言葉たちがたくさん詰まっていた。自分の中にこんなキラキラしたものが眠ってたなんて、私ははじめて知った気がした。
まだ眠っている彼の隣でもうすこし寝ていたかったけど、月曜の朝は早朝からミーティングがあるからどうしても部屋に帰らなければならなかった。すこしだけ悩んだ後に「昨夜はありがとうございました。五和(さわ)」と書き置きをのこして私は彼の部屋を出てきた。きっと眠った時間は三時間にも満たない。でも昨日の夜の出来事を思いかえすとそれだけで幸せが胸の中心から広がって、指の先から落ちる水滴にまで染みこんでいくような気がした。
と、私はふとミーティングのことを思いだしてまっ青になった、いま何時だろう? 急いで外に飛び出して時間を確認する──まずい、遅刻ギリギリだ。昌弘さんが待っている会社に彼女(候補)の私が遅刻ギリギリだ、と思いかえして一瞬また喜んで、あとは大急ぎで出社の準備をした。
