
■あらすじ
仕事バリバリの32歳OL、小島五和(こじま さわ)。28歳で最後の恋愛を終えてから、しばらく恋愛なんかしなくていいと思っていた彼女に訪れた30代最初の恋、そして失恋。その相手を見返すために、「恋愛マニュアル」を片手に、日々奮闘していく…
■作者プロフィール
志羽 竜一 1976年生まれ
慶應義塾大学 経済学部卒 東京三菱銀行退行後、三田文學新人賞を受賞してデビュー。
作品:「未来予想図」「アムステルダム・ランチボックス」「シャンペイン・キャデラック」など
※小説内で小島五和が使う「恋愛マニュアル」はNewsCafeトップページ中段リンクから閲覧可能です。
-前回まで-
仕事バリバリの32歳OL、小島五和(こじま さわ)。4年ぶりに恋に落ちた相手は、同じ会社の隣の部署に勤める小暮昌弘。彼と、酔って一夜をともにしたのだ。だが昌弘は、五和の後輩であり、全社のアイドル的存在の紀美子と付き合っていた。昌弘と紀美子が二人して自分を馬鹿にしていたことを知った五和は、絶望の中、「あした恋するキス講座」という恋愛マニュアルを知り、昌弘と紀美子を見返すことを心に決める。マニュアルの最初のレッスンは「誰か異性の連絡先を訊いてみること」。さんざんためらった挙句にこの関門を突破した五和は、自分が新しい一歩を踏み出したことを知る。
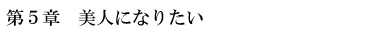
☆14
「なんかずいぶん嬉しそうじゃねぇか」
「その理由、知りたい? 知りたいっ?」
興味を押し売りする私に「ぜんぜん知りたくない」と答えて、傑(すぐる)は自動販売機から紙コップを取りだした。蛍光の緑色の液体がコップのなかで泡を弾かせている。
「傑にじっくり話してあげるから、今夜時間つくりなさいよ」
「だから興味ないって。どうせ恋愛マニュアルのことだろ」
「ふふ、知りたい?」
アホか、と彼は大きくあくびをした。今日もまるで仕事にやる気がなさそうだった。眠いならコーヒーでも飲めばいいのに。というか会社の自動販売機でメロンソーダを飲む人間なんて傑以外に知らない。
「どっちみち今夜はダメなんだよ」
「なんでよ」
「今日はキャバ嬢とデート」
「紀美子一筋なんじゃないの?」
声が大きいって、と傑は社内の廊下を見まわして言った。
「エヌキミは可愛い。キャバ嬢も可愛い。男は可愛い女の子に弱いのさ」
「それで自分も可愛くそんなもの飲んでるわけ?」
「コーヒーなんて飲んだら目がさめちまうだろ。会社ではぼんやり過ごすに限る。それにはメロンソーダが一番なんだよ。いまの時代は『なんとなくトロピカル』。五和(さわ)も覚えとけ」
「そんなことばっかり言ってないでちょっとは仕事したら?」
私は営業部へ視線を投げていった。昌弘さんはデスクにいない。そもそもお昼過ぎのこの時間、営業部はみんな外回りで部員はほとんど残っていないのだ。
「仕事をサボって女の尻追いかけてるなんて、そのうち嫁にも捨てられちゃうぞ」
「かまわないね」
いつになく冷静な声で傑は言った。
「仕事、もう飽きたんだよ」
傑は私に背を向ける。
「熱いものはいつか冷める。それもついでに覚えとけ」
ひらりと手を振って彼は部署に戻っていった。
私は大きくため息をついた。
二年前まで傑は営業部のキーマンだった。営業成績は常にトップクラスで上司からも一目置かれるような存在だった。顔つきだって今よりもぜんぜん引き締まっていたし、実のところPR部の女の子にだって人気があったのだ。つり上がった眉や筋の通った鼻、目の大きさとバランスのとれた豊かな唇の形は、良く見れば美形と言えなくない。性格はいまと変わらず適当な奴だったけれど、仕事への気迫が彼の雰囲気を精悍(せいかん)にしていたと思う。
彼の営業成績は努力のたまものだった。傑は誰よりも靴底を減らして顧客と関係を築いていたのだ。客本位の姿勢を貫いていた彼は呼び出されたら何時であろうとすぐに客先に駆けつけていたし、時には会社の利益が薄くなろうと上司を説得して案件を進めたりしていた。顧客からの信頼はあつく、部内からも頼りにされていた。すこしは休んで奥さんとの時間を取れ、と私がさとすくらいだったのだ。
彼が失速したのは二年前、彼が持っていた大口顧客の上位二社が、突然ライバル会社に奪われてからだった。新規顧客獲得に奔走していた時期で、二社から注意がそれていた。傑の管理ミスは否めなかった。
「女と一緒だよ。ちょっと目をそらすと浮気する。いつも見ていないとやきもちを妬く。信頼って言葉って、ちょっと白々しいよな。だって裏切る前までは必ず信頼は存在しているんだから」
よりによってそれは年末の出来事だった。毎年、年末には本社肝煎(きもいり)のクリスマスシャンパン発売イベントがあった。傑が担当していたグラスメーカーと食品メーカーとの共催だったそのイベントは、直前になって中止が決定された。他の部署とも(もちろんPR部も)連携して動いていたために、彼の失態は全社員の注目を受けた。
「まぁ会社人生、こんなこともあるわな」
と特別落ち込んだ様子は見せなかったけれど、以降彼は大口顧客から外され、彼自身も仕事に熱意を失った。
