
■あらすじ
仕事バリバリの32歳OL、小島五和(こじま さわ)。28歳で最後の恋愛を終えてから、しばらく恋愛なんかしなくていいと思っていた彼女に訪れた30代最初の恋、そして失恋。その相手を見返すために、「恋愛マニュアル」を片手に、日々奮闘していく…
■作者プロフィール
志羽 竜一 1976年生まれ
慶應義塾大学 経済学部卒 東京三菱銀行退行後、三田文學新人賞を受賞してデビュー。
作品:「未来予想図」「アムステルダム・ランチボックス」「シャンペイン・キャデラック」など
※小説内で小島五和が使う「恋愛マニュアル」はNewsCafeトップページ中段リンクから閲覧可能です。
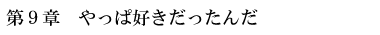
☆34
香月からは数日おきにメールが来ては、この雑誌のこの洋服を見てこいだとか、この化粧品を試してみろだとかいう指令が降りる。彼女の言葉通りに様々な洋服を試し、化粧品を試し勉強を重ねていくうちに自分にはなにが似合って、なにを敬遠すべきなのかが分かってきた。
「正直、ここまでよくなるとは思わなかった」
「師匠のおかげです」
「ますます精進せい」
そう言って香月は手を伸ばすと、ストローに口をつけていた私の顔を両手で包み、両耳を指で引っ張った。
「ジュースこぼれますって!」
大騒ぎする私を見て彼女は可笑しそうに笑ったまま、耳から指を話さない。まるで犬や猫のように香月にあやされている気分。でもそれがなんとなく嬉しかった。
いまから思えば私は美容についてもファッションについてもほとんどなにも知らなかった。そんな私に知識を植え込みセンスの磨き方を教えるのは並大抵の労力じゃなかった。昌弘さんにデートに誘われるようになったのも香月のおかげだ。
「万事、思った以上に好調に進んでます」
「へぇ。昌弘は落ちそうなの?」
「かなりいい調子だと思います」
いつものパンケーキ屋で、彼女はスワロフスキーの髑髏が配された上下のベロアスウェットを着て座っている。膝を組み、レモンスカッシュのストローから口を離して香月師匠は言う。
「でも気ぃ抜くなよ。安心した瞬間に、逆に自分が相手にハマったりするから。最後までしっかりツメて落とせ」
カッコイイ、カッコよすぎるよ香月師匠。まさしく恋愛必殺仕事人だ。彼女がタバコに火をつける。私がライターを持っていたらすっと差し出したい気分だ。
「新しい男のほうは? ちゃんと恋人探してるの?」
そう言われて、ふと加納さんのことを思いだす。すぐに首を振ってティーカップに口をつけた。傑の奴が変なことを言うからだ。いままでいちどだって加納さんのことを恋人候補としてなんて見たことがない。加納さんだって私のことをお客さんか、よくてもジョギング仲間くらいにしか思っていないはずだ。
「あ、サワ、誰か好きな人いるんだ」
「いませんよ」
「自分で気づいてないだけとか」
「だからいません!」
傑と同じことを言われて私の声は大きくなった。傑の奴まさか香月に私の話をネタとして提供したんじゃないだろうな。
「なんだよ急にムキになって。もしかして、その相手スグルだったりして」
「だれがあんな奴。たとえ離婚が決まってもぜったい慰めてやらない」
「離婚?」
と香月が顔をしかめたのはそのときだ。あれだけ注意されていたのに思わず祐理さんとのことを口に出してしまい私の心臓は止まりそうになった。
「いや、離婚っていうのはものの喩えで、ぜんぜんそういう事実があるわけじゃなく……」
私が焦っているのを見て香月は笑顔を作る。
「別にいいよ、知ってるから。最近詳しく聞いてなかったらちょっと驚いただけ」
「そうなんですか、びっくりしちゃったじゃないですか」
私は呼吸をととのえる。それでもまだ心臓の音は高鳴っている。この二人はどこまでシリアスにつき合っているんだろう。トシは傑が原因で傑と祐理さんが不仲になったと非難していたけれど、そのもともとの原因である香月と私はこうして師弟関係にある。あぁ、大人の男女関係って複雑だ。私は天井を見上げて大きくため息をついた。
「悪ぃ悪ぃ。うまくいってないのは知ってたし。ただ離婚するときはその前にちゃんとひとこと言えって言っておいたからさ。傑ひとりの問題じゃないジャン? もう別居してどれくらい経ったっけ」
「さぁ一年以上じゃありませんでした?」
「スグル、別居してんのかよ!?」
つか引っかけ問題かよ! と私は声をあげたくなる。もう香月は不快気な顔を隠そうともしなかった。
「あいつ、なにも言わないでコソコソと」
「そんな、知らなかったなんて、あの、えっと」
「もう傑に言ってもらちがあかない、こうなったら……」
「こうなったら? ちょっと、タンマ! 無理、無理ですから! 祐理さんところに押しかけるなんて真似、やめてくださいね。どう考えたって事態は好転しないんだし!」
「分かってるよ」
と香月はぜんぜん分かってなさそうな顔で言った。これはマズイ。どう考えてもマズイ。全身から血の気が引いて固まっていると、香月の携帯が鳴り「あ、仕事だ。じゃまた連絡するから」と私に声をかけて立ちあがった。
「香月さん、マジで! 絶対に変なことしちゃダメですよ!」
「分かってるって。はい、もしもーし、ちょっと最近なにしてんのよォー」
あぁ、やっぱりぜんぜん分かってない。私は頭を抱え込んだ。香月なら本気で祐理さんのところへ突撃しかねない。そうなったら確実に離婚決定だ。私のせいで。もちろん香月のせいでもあるけれど。というかもともと傑が悪いんだ。
「あぁ、でもどうしよう」
私はテーブルに突っ伏した。
ところでなんで香月は傑に離婚して欲しくないのだろうか。傑がシリアスすぎるとかえって困るからかな。だとしたら傑はやっぱりただのお客さんのひとりで、そう思うとすこし可哀想になってくる。恐るべし、恋愛必殺仕事人。血のかけらもない。こうなったら前もってひとこと傑に謝っておこうかな、と携帯電話のディスプレイを開いたけれど、すぐに考え直してやめた。香月くらいの女性なら、祐理さんの元へ突撃した後のことだって簡単に想像がつくはずだ。冷静になれば無茶なことはしないだろう、きっと。きっとね。
