
■あらすじ
仕事バリバリの32歳OL、小島五和(こじま さわ)。28歳で最後の恋愛を終えてから、しばらく恋愛なんかしなくていいと思っていた彼女に訪れた30代最初の恋、そして失恋。その相手を見返すために、「恋愛マニュアル」を片手に、日々奮闘していく…
■作者プロフィール
志羽 竜一 1976年生まれ
慶應義塾大学 経済学部卒 東京三菱銀行退行後、三田文學新人賞を受賞してデビュー。
作品:「未来予想図」「アムステルダム・ランチボックス」「シャンペイン・キャデラック」など
※小説内で小島五和が使う「恋愛マニュアル」はNewsCafeトップページ中段リンクから閲覧可能です。
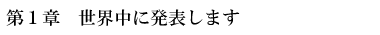
☆3
私が勤める会社は、もともと大手飲料メーカーのマーケティング部門が独立した小さな企業だった。当時は親会社から降ってくる仕事を細々とこなしていくだけの会社だったのだけれど、ヘッドハンティングされてきた加那山智子がPR部のトップとなってから会社の性格はがらりと変わった。親会社以外からも積極的に仕事の受注を受けるようになり、営業や経理、総務といった部署も拡充されていった結果、今では親会社からの受注なくとも独立採算のとれる中堅企業となった。
私がこの会社に転職してきたのは二十六歳のときだった。
二十八歳で最後の恋愛を終えてから(もっとも、はたしてそれを恋愛と呼べるかどうかわからないようなシロモノであったけれど)、しばらく恋愛なんかしなくていいと思ってた。それにあえて意識なんかしなくたって、どうせ彼氏なんかすぐにできるとも思ってた。
親会社からうちの営業部に小暮昌弘が出向してきたのは一年前、その頃から彼は私の憧れの対象だった。でもそれはただの憧れに過ぎず、挨拶を交わすとなんとなく一日の気分がいい、という人でしかなかった。営業とPRは隣同士の部署なのに、一週間も顔を合わせないことなんかざらにある。そのときも別に気にはならなかったし、顔が見られないとソワソワするなんてことも起こらなかった。要するに小暮昌弘は単なる風景の一部にしか過ぎなかったのだ。いればいいけど、いなくても気がつかない、そんな人。それが、たった一夜を境に、彼は私の景色にはいなくてはならない人に変わってしまった。
会議が終わってデスクに戻ってからも、私は通路のほうばかりにちらちらと視線を送っていた。どうやら昌弘さんはまだ会社に来ている様子がない。十時を過ぎると遅刻したのではないかと気が気じゃなくなってくる。目覚ましを掛けている様子なんかなかったから、もしかしたらあのまま眠りつづけているのかもしれない。だとしたら睡眠時間を奪ったのも、彼を目覚めさせなかったのも私の責任だ。
どうしよう、電話で起こしてみようかな。
でももし起きていたのなら、ずいぶん間抜けな電話になってしまうな。
考えているうちにいてもたってもいられなくなって、私はデスクを離れるとコーヒーを買いに廊下に出た。自動販売機は営業部の目の前にあった。コインを入れながら営業部をちらりと見るけれど、そこにはやっぱり昌弘さんの姿はない。ため息をついて、熱くなった紙コップに手を伸ばす。あちち、とカップを手にふり返ったときに、どん、と人にぶつかって私はそのまま淹れたばかりのコーヒーをこぼしてしまった。
「アッチィ」
とコーヒーがかかったズボンを大あわてで指でつまむ男の姿を見て私の心臓は止まりそうになった。
「昌弘さん」
「……小島さん」
すみません、と我に返った私はハンカチを取りだして彼のズボンに当てる。大丈夫だから、と彼はあわてて自分のハンカチを取りだした。
「すいませんでした」
「いや、ほんと大丈夫、気にしないで」
「でも」
「ほんと、大丈夫だよ。ありがとう、小島さん」
水色のクレリックシャツに淡いピンクのネクタイを合わせていた。175センチ以上あるすらりとしたスタイルにシングルスーツがよく似合っていた。すこし目尻が下がった、大きな目で私に微笑む。左耳にはかつてピアスをつけていた小さな跡が二つ残っている。この年になるとその痕がはずかしいんだ、と酔った彼は言っていた。この人と、今朝まで一緒にいたんだ。そう思って私は息苦しくなるくらい緊張してしまった。
「小島さん?」
「あの、あの、五和でいいです」
ありったけの勇気を振り絞って私は言った。
昌弘さんは顔を伏せる。その表情が、私には見えない。
さっと体から血の気がひいた。私は会社でなんの話をはじめようとしているのだろう。まだ彼の気持ちを聞いたわけでもないし、自分の気持ちだって伝えていない、お互いになんの了解もなく、たったいちど寝ただけじゃないか。もしかしたら、そんなことは絶対に考えたくはないけれど、彼にしてみたら酔った勢いで、とか、人恋しくなって、とか、ノリで、とか、グルーヴで、とか、朝のテレビ占いで「好きでもない女と寝ると吉」と言われて、とか、そんな理由かもしれないのに、なに私ひとりで盛り上がってるんだ!「ごめんなさい」
もういちど、こんどは早口で謝った。
「あの、あの、私、行きます」
背を向けて私は歩き出す。
その背中に「小島さん」という声が届いて私の足は勝手に立ち止まった。
「あのさ、なんていうか」
「……はい」
「昨日はありがとう」
「え」
「あの、こんど時間つくってもらっていいかな」
彼の恥ずかしそうな笑顔に、私は幸福のあまり体がバラバラになりそうになる。
「私、私、行きます」
どんな顔をしたらいいのかわからなくて、そのままPR部に戻った。手にした紙コップの中身が空のことにもしばらく気がつかなかった。
