
■あらすじ
仕事バリバリの32歳OL、小島五和(こじま さわ)。28歳で最後の恋愛を終えてから、しばらく恋愛なんかしなくていいと思っていた彼女に訪れた30代最初の恋、そして失恋。その相手を見返すために、「恋愛マニュアル」を片手に、日々奮闘していく…
■作者プロフィール
志羽 竜一 1976年生まれ
慶應義塾大学 経済学部卒 東京三菱銀行退行後、三田文學新人賞を受賞してデビュー。
作品:「未来予想図」「アムステルダム・ランチボックス」「シャンペイン・キャデラック」など
※小説内で小島五和が使う「恋愛マニュアル」はNewsCafeトップページ中段リンクから閲覧可能です。
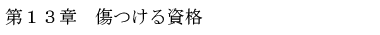
☆50
もう認めざるを得ない。
私は、モテてる。
いまやメールで連絡を取っている男の子は片手じゃ収まらない。デートの誘いだって週に二本以上ある。
「今日もデートですかぁ?」
という社内でのひと言が、バカにしたひと言じゃない。
もはやいまの私は出会った人の連絡先を訊くのがまったく苦にならない。男の子への受け答えも、タイプ別に対応できる。彼らをタイプ分けできるほど、母集団と経験値を持っている。ダイエットも、美容も、オシャレも、生活の一部になった。汗まみれのすっぴんで写っている写真の女とは、もう私は別人だった。
昌弘さんの「待つよ」宣言は、それを決定づけるものだった。
──でも。
それを全部合わせたって週末の加納さんとの出来事は私をひどく落ち込ませた。なんであそこまで話してしまったんだろう。せっかくここまで仲良くしてこれたのに。私が急ぎすぎてしまったから? なんでそんなに急いでいたんだろう? きっと昌弘さんと寝てしまったからだ。結局、私のミスだった。
会社でも仕事が手につかずに落ち込んでいるところへ、モテはじめた私への試練はさらに訪れる。
「正直に言ってください、五和さん、マサくんにちょっかいだしてます!?」
紀美子から会社の屋上に呼び出されました。いまどき会社の屋上への呼び出しとかいって、ありえない。テレビドラマの再放送でしか見たことない。だいたい誰なのよ、マサくんって。
「小暮さんです!」
そうですか。首をひねっていた私の疑問を先回りしていた紀美子が、泣きはらした目で私を睨んでいた。週末に昌弘さんとひと揉めあったのだろう。私と寝た週末だ、ないほうがおかしい。
「なんとか言ってください!」
そう叫ぶ紀美子を私はぼんやりと眺めた。そういえば紀美子、いたよね。
私はかつて、絶対にこの女だけは許さないと思ってた。だけど、自分が変わっていくうちに、その気持ちが薄れてしまったのだ。もうこの女の子への復讐心を糧(かて)にしなくても、私は綺麗になっていける。きっと、昌弘さんに対して関心を失っているのも同じ理由だ。もうすでに勝敗は決していた。司会業務を紀美子ではなく私が担当することになったとき、仕事にも恋にも私は勝ったのだ。
「五和さん、シラを切るつもりですか! マサくんにちょっかい出してるのは知ってるんです!」
「紀美子と小暮さんってつき合ってたの?」
「つき合ってるんです!」
なんだと? まだつき合ってる? マサくん、それはいただけないよ。と思うけれど、いかにも昌弘さんらしいとも納得する。結局いま私たちの力の関係性は、五和>マサくん>紀美子、となっているのだ。私が昌弘さんを占領し、昌弘さんが紀美子の思考を占領してる。
「つき合ってたなんて知らなかったわ」
「知らなくて当然です、他のみんなに気を使って、私、一生懸命隠していたんだから」
気を使って公表しなかった、なんて。バカじゃないの。まるでみんなのためみたいに言ってるけれど、そんなの自分たちのためじゃない。
私は紀美子を見つめた、これ以上ないくらい冷静に。
泣きはらしたように瞼(まぶた)は重そうだったけど、それでも彼女は美人だった。若くて、綺麗で、スタイルがよくて、抜群にオシャレだった。仕事も頑張るほうだし、よく気が利くと社内でも評判、これからが楽しみな若手社員の代表だった。
そう、彼女はまだ若いんだ。
昌弘さんには、子供同然だ。
そのとき私は唐突に気がついてしまった。私の目の前に立っている女の子は、四十がらみの男に遊ばれていた女の子のひとりなんだ。その証拠に、私に告白している彼から、まだ別れも告げられていない。都合のいい、適当に扱っていい女の子のひとりなんだ。
なんてことだ。彼女もまた、昌弘さんの犠牲者じゃないか。
「小暮さんが会社には黙っていようっていったの?」
「それがどうかしました?」
やっぱりね、と私はため息をつく。
「彼は傑(すぐる)さんと違って全社から注目されているし、私とつき合ってることがわかったら仕事にも影響あるんです!」
なんで傑の名前が出てくるのかはこの際おいておくとして。私は腕を組んで息を吐く。この子はずっと必死だったんだ。確かに私はひどいことを言われたし、ひどいことをされたと思う。でも、彼女は彼女なりに自分ではどうしようもならない苦しい世界を生きているのだ。
「別にちょっかいなんて出してないって。ただなんどかデートしただけ」
「じゃあなんでマサくんは私と距離をおこうなんて言うんですか!」
「わからないわよ」
「わかってるでしょ、私知ってるんだから! 五和さんがミュージカル行ったの!」
「……行ったけど、それがなんなのよ」
不意を突かれた私はうろたえた。
「五和さんは平気で人のことを傷つける」
「たかが舞台一緒に見に行っただけじゃない。それくらいで勝手に傷ついたフリなんてしないで! 私なんか……」
「傷ついたフリ? ひどいよ、五和さん。なんにも知らないくせして……」
彼女は歯を食いしばって銃弾のような視線を私に打ち込む。
「あのチケット……」
「なによ」
「あのチケット、クライアントが欲しがってるからって彼に言われて私が取ったんだから! 私が買ったの! 五和さんが彼と寝た夜のチケットよ!」
心臓が止まった。
「私がどんな気持ちだか分かりますか?」
「……」
「私、絶対に許さない」
そう言って彼女は怒りで顔を歪めると、きびすを返して屋上を後にした。
