
■あらすじ
仕事バリバリの32歳OL、小島五和(こじま さわ)。28歳で最後の恋愛を終えてから、しばらく恋愛なんかしなくていいと思っていた彼女に訪れた30代最初の恋、そして失恋。その相手を見返すために、「恋愛マニュアル」を片手に、日々奮闘していく…
■作者プロフィール
志羽 竜一 1976年生まれ
慶應義塾大学 経済学部卒 東京三菱銀行退行後、三田文學新人賞を受賞してデビュー。
作品:「未来予想図」「アムステルダム・ランチボックス」「シャンペイン・キャデラック」など
※小説内で小島五和が使う「恋愛マニュアル」はNewsCafeトップページ中段リンクから閲覧可能です。
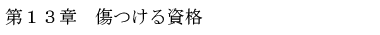
☆51
「ちょっと、サワさん話きいてんの?」
あれ以来、怖くて加納さんに連絡が取れない。
「エグザイルのライブ、取ったからね?」
加納さんからも連絡はない。着信があるのはかつての練習相手の男の子たち。
「あ、ごめん、やっぱその日行けない」
「な、なんだよいきなり」
トシが大袈裟に椅子からずり落ちる。あー、私、もすごくひどいことしてる。でもどうせなら、これで私のことを嫌な女だと呆れて欲しい。そのエグザイルのチケットで、他の女の子を誘って欲しい。
「じゃあ、いつなら行けるんだよ」
「いいよ、もうチケットとっちゃったんでしょ。他の人と行ってきなよ」
「うるせぇな。いいからいつなら行けるんだよ」
私の対応がおざなりになればなるほど、相手は必死になってくる。私の名前はもうトシの思考を占領してしまっているのだ。いちど占領してしまった後は、ほとんど労力を使わなくてもその占領は維持される。どれもこれもあした恋するキス講座の言うとおりだ。でも、いまは私をそっとしておいて欲しい。
「私だって忙しいの知ってるでしょ。ほかの誰とでも行ってきなさいよ」
そう言って店を出る。
トシなんか傷ついたって当然なのだ。あれだけ傑を傷つけたのだから。
でも、私はトシを傷つけて当然なのだろうか。私が昌弘さんに傷つけられたから? 私が紀美子に傷つけられたから? 誰かこの堂々巡りを止めて欲しい。私はこんなことがしたいわけじゃなかった。
加納さんに嫌われたいわけじゃなかった。
誰と話していても、加納さんのことしか考えられない。それならひとりでいたほうがいい。それなのに無性に誰かと話したくなる、話していないと不安になる。
「五和、聞いてるのかよ」
「あ、ごめん」
「勘弁してくれよ。各メディアはどれくらい呼べそうなの」
「あー、それ。まだハッキリとは……」
会議出席者の視線が私の上で重なる。重く濡れたような空気。「じゃあ制作チームからの報告を」という傑の声で、その空気が霧散し会議が進み出す。いまや傑は企画の中心人物となった。誰もが無理だと思った二十代OLに人気の大手アパレルブランドをこの企画に巻き込み、あそこのブランドがやるならと他社ブランドも相乗りをはじめた。傑が提案した場内をダンスフロアにするというアイディアも、自分でレコード会社と話をつけ、当日のライブ音源をシャンパンミックスとして発売する約束まで取りつけた。もう、社内で傑のことを笑う人間はひとりもいなかった。
「お前、いい加減にしろよ」
会議が終わったあと、社外の喫茶店に私を呼び出した傑はため息をついた。
「なにボンヤリしてんだよ。そんな暇ねぇだろ」
「ごめん」
「謝んなくたっていいから仕事しろよ。お前が立ちあげた企画だろ」
「わかってるって」
「わかってねーよ。もう時間ないんだよ。そんななか、みんな頑張ってんだろ」
傑はコーヒーに口をつける。もうメロンソーダは彼に必要ないんだ。
「気晴らしに、メシでも行くか? 久しぶりにカノウとか」
私はその名前を聞いただけで震え上がる。
「やだ、絶対やだ」
「……お前、加納さんとなんかあったの?」
「関係ないでしょ」
「なくねーよ、お前もしかしてまだあのくだんねぇマニュアルで遊んでんじゃないだろうな。仕事ほっぽらかしてそんなことばっかりしてると……」
「傑にいわれる筋合いないでしょ! 傑だってこの一年私と同じだったじゃないの」
痛いところを突かれた私は、カッとして声を大きくした。
「同じことなんかしてネェよ。確かに仕事に熱はなかったけどよ、人の気持ちで実験するようなことはしてねぇ」
傑の言葉が加納さんの視線を思いださせた。私はぐっと唇を噛む。
「だからはじめから言ってたんだよ。人の言うこと鵜呑みにしたって、幸せになんかなれねーんだ」
「うるさい! 奥さんひとり取り戻せない男が偉そうに言わないで。傑の仕返しだって私が代わりにしてあげてるんでしょ!」
「なんだとコラ? ……お前まさかトシにまで同じことしてんじゃねぇだろうな」
「傑がこのままコケにされてたら悔しいから傑のためにしてるのよ!」
「そんなこと頼んだ覚えはねぇ! アイツとはオレも祐理も縁を切ったんだ!」
「でもトシは傷ついて当然よ」
「お前、どうかしてるぞ!」
傑が身を乗りだす。彼が私を心配してくれているのは痛いほど伝わる。でも私はいまそれを受けとめることができない。
「私の気持ちなんか傑にはわからない! 私のことは放っておいて」
「勝手にしろ」
彼はコーヒーを飲み込むと千円札を置いて店から出て行く。わたしはどうしようもなく、メロンソーダが飲みたくなった。
